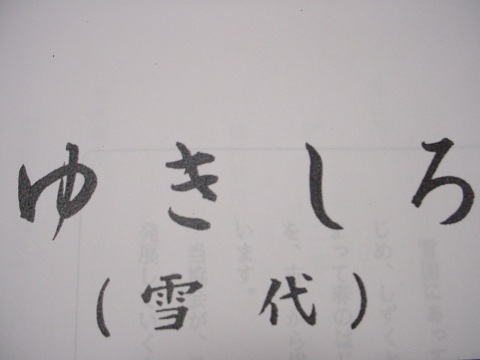
第91号
(発行者)
社会福祉法人 富山県視覚障害者協会
〒930-0077
富山市磯部町3丁目8番8号
電話 (076)425-6761
Fax (076)425-9087
Eメール:bcb05647@nifty.com
Homepage:https://toyama-ssk.com/
(発行責任者)
会長 塘添 誠次
(令和7年6月発行)
この「ゆきしろ91号」は令和6年10月1日~令和7年3月31日までの分を掲載しています。
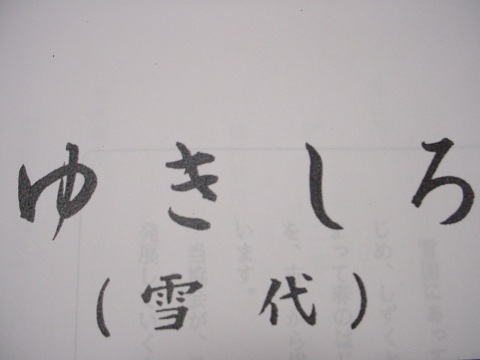
第91号
(発行者)
社会福祉法人 富山県視覚障害者協会
〒930-0077
富山市磯部町3丁目8番8号
電話 (076)425-6761
Fax (076)425-9087
Eメール:bcb05647@nifty.com
Homepage:https://toyama-ssk.com/
(発行責任者)
会長 塘添 誠次
上の題字は 鶴木大壽 氏によるものです。
【ゆきしろ(雪代)の意味】
雪国にあって、大地が春の雪原と接する部分で静かに融けはじめ、しずくとなり、やがてかすかな流れをつくり、それが集まって春のはじめの雪どけ水となって音をたてて大河に注ぐ様を、古くから俳句における春の季語として「雪代(ユキシロ)」とよばれています。
当協会が、このしずくが集まって大河をつくるように大きく発展していくよう、願いを込めて命名いたしました。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【ゆきしろ91号 目次】
《大会参加報告》
◆第31回北信越ブロックサウンドテーブルテニス大会(石川大会)
◆令和6年度第2回全国委員会及び令和6年度第2回全国代表者会議
◆「第24回富山県障害者スポーツ大会(卓球競技会)」参加報告
今年は、1825年にルイ・ブライユが点字を考案して、200年という節目の年に当たります。この点字のおかげで視覚障害者の有効な文字として私たちに伝わり、文化を育んできました。日視連は3年前から点字考案200周年に向けたイベントを行っており、今年も盛大なイベントが予定されています。
今回は、そのブライユの生い立ちと点字を考案した流れ、日本点字の誕生、点字に対する思いについて触れてみたいと思います。
ルイ・ブライユは1809年、フランスのクーヴレというパリから東に約40㎞にある小さな村で生まれました。お父さんは、馬具職人として家計を支えていました。3歳の時に父の仕事を真似ていて手を滑らせ、鎌形ナイフで自分の右目を刺してしまいました。その当時の医学では治すことができず、左の目も炎症を起こして、5歳の時には全盲になっていました。
ブライユが通っていた教会のパリュイ神父は、ブライユが聡明な子であることを見抜き、学問と信仰を教えました。そして、神父はブライユが学問を続けられるようにいろいろな後押しをしてくれました。町の学校で2年間学び、その後、パリの盲学校に進むことができました。
10歳の時に入学したパリの盲学校は、ヴァランタン・アユイが作った学校で、読み書き・算数・歴史・地理などの一般教養と、音楽と、手に職を付けること、の三つを目標としていました。
学校では、紙に普通文字を浮き出させた本を手でさわって読んで勉強していましたが、理解するのは大変で、速く読むことも、自分で書くこともできませんでした。
新しく着任した校長ピニエは、当時の学校で使われていた文字は読み書きの方法として効率的でないと感じていました。
その頃、バルビエは軍隊の夜間でも命令が伝えられる暗号として、12点の凸点方式の盲人用文字を考案していましたが、軍隊では取り上げてもらえず、それならば盲人に役立つだろうと思い、書く道具まで開発しました。
校長ピニエはこの文字が有効と考え、生徒を集めて実験したところ、生徒たちは即座に凸点方式が分かりやすいと評価しました。
ブライユはこの方式の凸点の読みやすさに着目し、改良を加えて独自の体系を作ろうと地道に取り組みました。15歳になる頃には、指の下にすっぽりと収まる6点からなる文字にたどり着いていました。六つの点を組み合わせると全ての文字、数字、アクセント記号、句読点を表すことができると考えました。
そして、とうとう16歳の時、1825年にブライユは目が見えない人が自由に、速く、読んだり書いたりできる文字「点字」を作り上げました。
ところが、1840年に就任した校長デュフォーにより、一時ブライユの点字が禁止されたことがありました。自分のアイディアである新しい浮き出し文字を普及させようと思ってのことで、盲人も晴眼者と同じ読み書きの方式を使うべきだというのですが、一説には、自分が点字を読み書きできなかったからだというエピソードも残っています。
しかし、副校長のガデはブライユの点字が実用的であることに気づき、デュフォーを説得してブライユの点字を復活させました。
しかし、ブライユは小さい頃から病弱で、26歳で結核と診断され、徐々に弱っていき、1852年に43歳で亡くなりましたが、その2年後の1854年にフランス政府がルイ・ブライユの点字体系を盲人が読み書きする公式な方法として正式に認めました。
この点字は急速に世界各国に広がり、日本では、1887年(明治20年)に、ローマ字式の点字が初めて使われました。その時の生徒の感激を目の当たりにした東京盲唖学校の教頭小西(こにし)信八(のぶはち)は、何とか日本語の点字を作りたいと考えました。
そして、先生や生徒たちでいろいろな案を出し合って研究を進め、1890年(明治23年)の11月1日に教員・石川(いしかわ)倉次(くらじ)の案が日本の点字として採用されました。
この点字のおかげで、1928年(昭和3年)に国政選挙で点字投票が初めて認められ、1949年(昭和24年)に大学受験、また、1973年(昭和48年)に司法試験などで点字受験が認められるようになりました。
今日では、音声で様々な情報が手に入るようになりましたが、点字は今も変わらず視覚障害者の指先で読める大切な文字です。近年、中途失明者が増えており、点字離れという言葉を聞きます。点字を読み書きできるようになるためには、時間がかかりますが、根気よく練習すれば読み書きができるようになります。墨字が読み書きできなくなった人は、是非点字を習得しましょう!
《大会参加報告》
◆第31回北信越ブロックサウンドテーブルテニス大会(石川大会)
令和6年10月19日(土)・20日(日)、第31回北信越ブロックサウンドテーブルテニス大会(石川大会)が石川県金沢市の石川県立盲学校において開催されました。
富山県からは選手6名(林(はやし)大志(ひろし)、徳市(とくいち)和美(かずみ)、中川(なかがわ)慎也(しんや)、竹山(たけやま)翔(しょう)、本江(ほんごう)とみ子(とみこ)、池田一義)と県派遣審判・鳥崎(とりさき)さとみさんの計7名が参加して、19日の10時に鳥崎さんの車、運
転で石川県立盲学校へ向かいました。 13時30分から体育館で開会式が始まり、米島(よねしま)理事長の挨拶が始まった時に雨が降り出し、体育館の屋根を叩く音が大きくて試合が出来ないのではと思いましたが、10分ほどで雨はやみ、ほっとしました。
米島理事長の挨拶の後、競技上の注意と会場案内があり、14時から個人戦が始まりました。
まず予選は、3人~4人のグループに分かれてリーグ戦を行い、女子A(アイマスクあり)の部は各組1位、2位の人が決勝トーナメントへ進みました。 男子A(アイマスクあり)と男女混合B(アイマスクなし)の部は、3組に分かれて戦い、各組1位の人が決勝リーグ戦に進みました。
今大会は厳しい判定(ラケットの角度60度未満)をする審判がおられ、リズムを崩す選手が多くみられました。
そんな中、富山県選手は一生懸命頑張りました。結果は、徳市和美さんが2位、池田一義が3位、本江とみ子さんが4位に入賞しました。後の人は残念ながら予選敗退でした。
試合が延びて18時30分ごろにようやく終わり、宿泊先である西インターの「テルメ金沢」へバスで向かいました。宴会の時間に間に合わないため、お風呂に入らないまま懇親会に行きました。
食事は焼肉料理でしたので、焼くのに苦労しながら食べました。美味しかったですが、ちょっとびっくりしました。食事の後、温泉に入り疲れをいやしました。
20日は、8時30分から団体戦が行われ、富山県チームは頑張りましたが、Aチームが福井県Bチームに、Bチームが石川県Aチームに共に1対2で負けました。
大会は12時に終了し、帰りに祝勝会を軽く行ない、16時に富山駅に着きました。お疲れ様でした。
来年は富山県で開催となります。今年以上に頑張りたいと思いますので、皆さん、また応援よろしくお願い致します。
「日本視覚障害者団体連合北信越ブロック各県の代表者並びに青年部及び女性部の会員が一堂に会し、福祉や職業など当面する諸施策や課題について討議を重ね、視覚障害者の自立と社会参加の促進を目指すとともに、共生社会の実現と視覚障害者福祉の推進を図る」ことを目的として、第10回日視連北信越ブロック大会が11月30日(土)・12月1日(日)にアートホテル新潟駅前で開催されました。
1日目は開会式終了後、研修会、講演の後、二日間に亘り代表者会議・青年部・スポーツ協議会・女性部協議会、また、2日目の9時から10時30分まで、ロビーにてミニ福祉機器展と地域活動支援センター日だまりの授産品販売が行われました。
加えて、能登半島地震や豪雨災害に対する義援金活動も行われました。
以下は、その内容です。
「能登半島地震から学ぶ」をテーマに、講師2名からお話を伺ったのでその概要を報告します。
1.能登半島地震における地域の状況と視覚障害者支援の取り組み
石川県視覚障害者協会理事長 米島(よねしま)芳文(よしふみ)先生
令和6年能登半島地震の特徴としては、① 大規模、広範囲に被害が発生。② 陸・海・空のアクセス手段が遮断。③ 断水、停電、通信障害が長期化。④ 避難所運営が困難。⑤ 1.5次避難所、2次避難所が開設。⑥ みなし仮設住宅等での生活が始まる。⑦ 仮設住宅の建設が進む。⑧ 家屋の公費解体が始まる。⑨ 地震・豪雨による複合災害が発生。⑩ 地域復興計画の検討が始まる。等が考えられ、その経過については、
① 緊急期=発生から一週間。② 応急期=発生から数ヶ月。③ 復旧期=現在。④ 復興期=未だ至っていない。とたどっている。
石川県視覚障害者協会としても、令和6年能登半島地震視覚障害者支援本部を設置し、① 石川県が進める災害対策に協力。② 能登地区自治体が取り組む活動に協力。(社会福祉法人石川県視覚障害者協会、特定非営利活動法人金沢市視覚障害者地域生活支援センターが連携して取り組む)を目的に活動中である。
また、令和6年能登半島地震視覚障害者支援本部の活動として、① 視覚障害者の安否確認と支援に必要な情報収集。② 1.5次避難所における支援。③ 2次避難先における支援。④ 災害見舞金の取り扱い。⑤ 公費解体手続きの支援。⑥ 医療機関退院に向けての支援。⑦ 仮設住宅入居に向けての支援等である。
なお、被災者支援の具体例として必要物品の貸し出しがある。
必要物品の貸出品目。① 携帯電話充電ケーブル。② 白杖。③ 視覚障害者用音声時計。④ プレクストーク。⑤ 拡大読書器。※1.5次避難所、2次避難所において一般避難者向けにシニアグラスを配布。
2.日本口-ビジョン学会パンフ
「災害が起きたときのことを考えていますか?」「被災してしまったら」を中心に
眼科医 新潟県視覚障害者福祉協会評議員 張替(はりがい)涼子(りょうこ)先生
○「災害が起きたときに考えておきたい7つのポイント」
(1)一緒に逃げてくれる人をさがしてお願いしておきましょう。
(2)避難行動要援護者として登録しましょう。
(3)避難所、避難ルートを確認しましょう。
(4)災害用伝言ダイヤル171を知っておきましょう。
(5)見えにくい方用の非常持ち出し品をリストアップしましょう。
(6)自宅の耐震化や、必需品の準備・備蓄を行いましょう。
(7)早めの避難を心がけましょう。
○「被災してしまったら」
【避難所ですごす場合】
(1)避難所の管理者に目が不自由であることを伝えましょう。
(2)目が不自由であることを周囲の方に知らせましょう。
(3)生活上必要な配慮を周囲の支援者などに具体的に伝えましょう。
(4)当事者団体や点字図書館などに連絡しましょう。
【被災した自宅にやむを得ず避難する場合】
(1)目に障害のない人に安全上の問題を確認してもらいましょう。
(2)食料・水・簡易トイレなど生活に必要な物資を確認しましょう。
(3)電話やメールなど、非常時の連絡手段を確保しましょう。
(4)家族や支援者に自宅に避難していることを知らせましょう。
【インターネットでチェック】
○内閣府ホームページ(防災情報のページ):防災情報のほか、災害発生時には 被害状況・政府の対応などが随時掲載されます。
○災害用伝言ダイヤル171:個人の安否情報を音声で登録できます。毎月1日に使用練習ができます。NTT東日本とNTT西日本が提供しているサービスです。
○災害用伝言板web171:個人の安否情報を文字メッセージでインターネットに登録できます。毎月1日に使用練習ができます。NTT東日本とNTT西日本が提供しているサービスです。
◎助言
アドバイザー 日本視覚障害者団体連合会長 竹下(たけした)義樹(よしき)先生
○災害に対して眼科医とともに活動できるようになってきた(東日本大震災頃から)。非常にいいことだと思っている。
○日盲委(日本盲人福祉委員会)が、災害対策本部を継続して活動している。
○災害対策基本法に、新規に福祉の支援が入った。
◎研修会を終えて
能登半島地震やその後の豪雨被害などに対応された石川県視覚障害者協会や関係の方々のご苦労が伺え、頭の下がる思いで聞いた。まだまだ活動は続くであろうが頑張って頂きたいものである。
また詳しく解説された日本ロービジョン学会パンフ「災害が起きたときのことを考えていますか?」「被災してしまったら」は、弱視者だけでなく視覚障害者全体にも意義ある資料と思われるので、一読をお勧めしたい。著作権の関係で掲載できないが、日本ロービジョン学会ホームページからダウンロード可能。
13時15分から、越後・西の間において、演題「中央情勢報告」と題して開催されました。
大きな二つの項目があり、一つ目は、重点課題に対する取り組みについて。 (1)マイナ保険証に対する対応について
視覚障害者の認証をどうするか。
あはき師は患者のオンライン認証をどうするか。
まだまだ課題が多いとのこと。
(2)移動支援について
踏切における安全対策。横断歩道の白線の敷設方法変更に対する対応など、少しずつ移動しやすくなってきているとのこと。
(3)同行援護
サービス提供責任者の要件の緩和。移動支援従事者養成のカリキュラムの変更と新テキストが作成されるとのこと。
(4)あはきの報酬について
診療報酬の改定と往療における制度変更。1局所100円上がるとのこと。
(5)就労について
視覚障害者が、会社や治療院において、介助者の助けを得られるとのこと。
(6)視覚障害者リンクワーカーの養成について
医療と福祉の連携ということで、眼科クリニックにおいて相談員を配置して行くとのこと。
大きな二つ目は、日視連の新たな取り組みについて。
(1)5協議会との懇談会の開催
それぞれの現状や課題について意見交換を行った。
(2)歩きスマホとナビシステムの取り扱いについて
近年は視覚障害者のためのナビシステムが広がっており、他方で歩きスマホに対する警告を発し続けている。そうした中でナビシステムをどのように位置づけどのようにルール化するかが問われている中で、関係者と懇談会を開催し話し合った。
(3)あはきと理療科教育の未来を考える懇談会
理療科存続とあはきによる職業的自立のための条件をどのように定義するかを検討している。年度内には中間報告書を取りまとめる予定であるとのこと。
(4)能登半島地震に対する支援
能登半島地震に対する支援は、今も続けられているとのこと。
など、約1時間にわたり熱く、熱く語られた。本当に、頼もしい竹下義樹会長です。
午後4時30分から会場を移して開催。出席者の自己紹介、その後正副議長の選出に続いて議事に入りました。
1.日視連北信越ブロック報告
日本視覚障害者団体連合北信越ブロック長 米島芳文
令和6年1月1日に発生した能登半島沖を震源とする地震に際して、北信越各県から寄せられた義援金に対してお礼が述べられました。
2.日視連あはき協議会報告
長野県視覚障害者福祉協会理事長 青木(あおき)勝久(かつひさ)
令和6年6月より保険取り扱いにおいて診療報酬の改定がなされた事。以前からマッサージの報酬単価の低いことが指摘されていた現状で、今回大幅に1局所について100円の値上げ。また、令和6年10月より訪問等施術において往療料の値上げがなされた事等報告がなされました。
3.日視連全国大会提出議題審議
ここでは長野県から1題、新潟県から1題の提出が決まりましたが、いずれも原案で出されていた文章に修正を加える形で、二日目の会議の席で決議されました。
① 長野県
危険防止のための歩きスマホの禁止、併せて視覚障害者のスマホによるナビシステム利用時の移動の安全確保
この二つについてルール化し、新たに道路交通法の規則を定める。
② 新潟県
国は医療と福祉の連携を主導し、視覚障害者リンクワーカーの育成やスマートサイト機能を全国に充実させるための助成制度を整備すること。
4.「光の泉賞」候補者推薦
今回の開催県である新潟県より、上越市の吉田(よしだ)一枝(かずえ)氏(上越地区の会長を務めている吉田浩氏のお母様)の推薦が了承されました。
5.各県情報交換
ここではそれぞれ各県が取り組んでいる重点項目などが紹介・報告がなされました。
① グランドソフト、サウンドテーブルテニス以外でブラインドスポーツの新しい競技を北信越全体で取り組んで見てはとの意見が出された中で、1週間前に石川県においてフライングディスク体験交流会が福井県、富山県等、県をまたいでの参加をいただき開催できたことが報告されました。
② 令和元年10月に発足した、災害時における長期避難者の生活(高齢者や障害者、子供等)に対する福祉支援を行うDWAT(ディーワット)災害時の視覚障害者支援者マニュアルを活用し、毎年実施されている研修会に当協会も資料提供等で協力していることが富山県から報告としてなされ、同時に各県に資料配布・活用していただければとのお願いがなされました。
6.次年度行事予定確認(担当県別報告)
令和7年度の北信越管内で開催予定の行事について
・グランドソフトボール大会(石川県) 令和7年6月8日(日) 場所 野々市市健康広場
・北信越会長会議(福井県) 令和7年8月21日(木)・22日(金) 場所 未定
・STT大会(富山県) 令和7年10月18日(土)・19日(日) 場所 呉羽ハイツ
・北信越ブロック大会(長野県) 令和7年11月29日(土)・30日(日) 場所 長野駅前
以上、今回の会議報告になりますが、北信越管内での大きな大会として、令和7年9月3日(水)・4日(木)の両日にわたり新潟県において、全国視覚障害女性研修大会の開催が報告され、多くの皆様の参加(男性も含む)が呼びかけられました。
スポーツ・青年部協議会は新潟県の藤林さんに議長として、全ての県から当事者が出席して開催されました。
スポーツ協議会では主に日視連スポーツ協議会からの伝達と、北信越ブロックSTT大会の要項について話し合いました。
青年部協議会からは2024年のインクルーシブ教育向けのブラインドスポーツ体験会の報告、2025年開催予定のゴールボール初心者大会のお知らせなどをスポーツ協議会長の濱野からお伝えしました。
さて、問題はここからでした。北信越ブロックSTT大会の大会要項については大激論でした。
2024年のこの大会(石川県)では大会要項を大きく変更されました。団体戦では従来、アイマスクをした男性同士、アイマスクをした女性同士、アイマスクをしないどなたでも同士の3戦で勝負する形式でした。
2024年はこれをシャッフルして、アイマスクをしてる人としてない人の対戦が可能になりました。
理由としては「参加者の不足と、上手くなれば全盲でも弱視に勝てるから」とのことでした。
この話、何かおかしい。そもそも対戦をシャッフルしても参加者不足には大して影響がない。また、全盲でも弱視に勝てるかどうかはどうでもよく、公共の大会では類似した条件下で競うものです。上手な人お一人の声が大きくても全体の理屈を曲げるべきではない。「オレツエー」はよそでやっていただきたい。
しかしながら現状、大会要項を決定する場がないこともあり、石川県の要項を否定することができません。そこで2025年の富山県大会は元の要項に戻し、次回、2025年度のスポーツ部協議会で新要項を決定することにしました。激論でした。議長の藤林さんが気の毒になるほどの激論でした。
青年部協議会では大きな出来事が2つありました。
まず、先述したように全ての県から当事者が出席しました。これは私の人生の中で初めてのことでした。いつも当事者の参加のない2県が「主催県だから」「STTの新要項をゴリ押ししたいから」といった理由ではありましたが、それでも全県が揃うという事実は嬉しいものでした。
もう1点、石川県チームが20代の男性を連れてきました。30代の男性も連れてきました。ビックリしました。毎年、「青年」というには憚られるオッサンが集まって、「若い人いないよねー」と愚痴を言い合う場でしたから、本当に羨ましかったです。我々も諦めてないで頑張らないとです。
長時間の協議会でしたが、充実した時間になりました。
女性部協議会がアートホテル新潟駅前4階で開催されました。北信越5県全員参加で、議長に全国委員の富山県の延野と新潟県の渡貫(わたぬき)さんとで活発に意見交換がされました。
以下は協議された内容です。
1.令和7年に開催される第78回全国福祉大会千葉県大会に提出する議題を決めました。
物価高騰の折、障害者は生活が困窮しています。障害者基礎年金の増額を要望します。
2.第71回全国視覚障害女性研修大会新潟県大会に提出する議題を決めました。
視覚障害者が買い物や飲食しにくくなっています。セルフレジやタッチパネルでの操作が困難な場合、人的サポート支援が受けられるようにして欲しい。また、有人窓口をなくさないで欲しい。
3.第71回全国視覚障害女性研修大会新潟県大会のレポートテーマ案を決めました。
視覚障害の私たちが介護する立場になったときにあなたららどうしますか。
今回の大会参加者は120人で、富山県からは16人が参加しました。参加者は昨年より増えましたが、コロナ以前の状態には戻っていません。
今後はどのように参加者を増やしていくかが課題となりますが、コロナ禍で行われていたオンラインよりは直接会っての会議の方が話しやすく、お互いの気持ちが伝わりやすいと実感しました。また、人と人との触れ合い、交流ができたのが大変良かったと思います。
次回は、令和7年11月29日(土)から30日(日)にかけて長野県で行われます。多数の参加をお願いします。
今年度の文化祭は、下記の通り実施されました。コロナ禍の影響は5年もたち、ようやく以前の状態に復帰したと思います。
目的
日頃の生きがい活動の発表およびチャリティーバザー等を通じて、視覚障害者と地域の方々とのふれ合いや、情報交換を促進する場とする。さらに参加者相互の親睦と友情の輪を広める。そして、視覚障害者の文化の向上と、福祉の増進を図る。
日時:2024年10月13日(日)10:00~
会場:富山県視覚障害者福祉センター
日程
1.開会 10:00
2.アトラクション 10:20
(昼食)
3.生きがい教室発表 13:00
4.閉会 15:00
アトラクション 10:20~11:30
邦楽演奏会(箏、尺八演奏)
講師…生田流箏曲正弦社 直門 大師範
正弦社かたかご会 代表 水谷(みずたに)佳代(かよ)氏
都山流尺八 竹琳軒 大師範
邦楽ネットワーク富山 主宰 東海(とうかい)煌山(こうざん)氏
曲名…ふるさと、花は咲く など
会場…センター研修室
箏と尺八の演奏があり、その和楽器の音色やメロディーを堪能しました。
演奏が済んだ後、楽器に触らせてもらい、演奏の仕方等を一人一人手をとって指導していただきました。
しかし、私の感想ですが、尺八では綺麗な音を出せる者がほとんどいなかったと思います。和楽器演奏の難しさを感じた次第です。
催し物
1.生きがい教室発表 研修室
コーラス、民謡、カラオケ等
2.無料理療施術コーナー
(文化祭の目玉の一つと思います)
3.福祉機器展
音声体温計等
4.用具展示
点字器、拡大読書機、白杖等
5.バザー等
茶席、飲食品販売、ボランティアの手作り作品販売等
6.その他 興味のあるものが多くありました。
協力ボランティア団体…コスモスの会、あゆみ会、ひまわりの会、声のライブラリー友の会
ボランティアの皆さんの協力を感謝しています。
この事業は、共同募金の分配金で実施しています。
感想
文化祭は、内容、参加者共に以前と変わらないくらいに復帰しました。そして目的にあるように、視覚障害者を一般に理解していただくよいチャンスだと思います。また、懐かしい人との再会がありとても有意義でした。
令和6年度の三療研修会が11月10日(日)午後1時から富山県視覚障害者福祉センター研修室で参加18名で行われました。
今回は前半に「もし姿勢が気になりだしたら」と題してお話と運動をし、後半には最近の三療をとりまく現状について話し合いを、理学療法士の濱野昌幸氏(県協会理事)をお迎えして行われました。
はじめに視覚障害者がなりやすい悪い姿勢、診方、矯正のための運動について話をしていただき、その後、実際にモデルさんに出ていただいて姿勢を診て、視覚障害者がなりやすい、見受けられる姿勢についていろいろ説明される。
希望者の人の姿勢も診てもらう。診てもらった人は「そうですか」「やっぱりね」「これから気を付けます」などと感想を述べておられました。
そして「背伸び」と「胸を張る」運動の指導をしてもらいました。
後半は最近の三療の現状として、治療院に勤めている人の話、デイサービスに勤めている人の話など、個々の職場の話や訪問マッサージが最近少なくなったなどいろいろ話がでていました。
中途での障害者も増えていますがこれからの視覚障害者の職域の拡大も考えて開拓していく必要がありますね。
・6月30日(日) 三療部会・総会を開催
午前10時から盲人ホームにて7名参加。
会員の家族、ガイドさんへの治療奉仕を行い、他はそれぞれ施術交換を行う。
午後1時から令和6年度の総会。6名出席。
事業報告、決算、事業計画など行い、その後いろいろ情報交換、今後の部会での勉強したいことなどを話し合う。
・10月13日(日) 文化祭で治療奉仕を行う。
午後1時から2時50分まで。
6名で15名に施術。
思ったより少ない人数だったが、喜んでいただく。
・11月10日(日) 三療部会を開催
午前10時から盲人ホームにて三療部会を開催。参加3名。
家族1名に治療奉仕して他はそれぞれに技術交換を行う。
午後1時から研修室にて三療研修会に参加する。
前半に「もし姿勢が気になりだしたら」という姿勢を正しくする話と運動を講師にしていただき、後半で「最近の治療院、デイサービス事業所、施設などの状況について」ということで、いろいろ話し合う。
・令和7年3月9日(日) 三療部会を開催。
午前10時から盲人ホームにて3名の参加でそれぞれ施術技術交換を行う。
午後1時からは和室にて8名の参加で、「肩甲骨はがし」のDVDを見ながらそれぞれ見える人が見えない人に映像を見ながら実際にやっていることを説明しながらやってみせてくれる。
2時すぎになり盲人ホームへ移動してベッドを使ってそれぞれに思い出しながら実際にやってみる。
にぎやかに体験しながら楽しそうでした。これを持ち帰って実際の現場での施術に活かしていければと思います。
令和6年度の更生相談会、並びに結婚相談室、意見交換会は12月8日開催されました。33名の参加で午前10時より更生相談会が行われ、「協会事業の今後」をテーマにして進められました。
県への要望事項については、継続している23項目と新たに加えた3項目を1項目ずつ事務局が読み上げ、それに対する県からの回答を塘添会長が説明する形で行われました。トイレやバス停の音声案内が聴きやすくなってきていることや、音声信号機も少しずつ増えているとのことでした。
続いて宿泊研修について討議しました。最近宿泊料金が高くなってきていることや、参加人数が減ってきていることなど、いろいろ問題がありますが、これからも協会執行部が担当して開催されることになりました。
午後1時から、事務局から令和7年度の事業計画の説明、続いて山内副会長から令和7年5月24日(土)~26日(月)に開催される「第78回全国視覚障害者福祉大会・千葉大会」参加計画について、日程の説明のあと意見交換会が行われました。
今後の協会の事業に対し、参加者を増やしていきましょうと言う意見が出ました。また、マイナ保険証の使い方については、使いながら問題を解決していこうとのことでした。
結婚相談者はありませんでした。最後に懇親会があり、短い時間でしたが親睦をふかめられ、3時に閉会となりました。
◆令和6年度第2回全国委員会及び令和6年度第2回全国代表者会議
早春の候、3月12日(水)午後、全国委員会と日視連・竹下会長との意見交換会、3月13日(木)午前に全国代表者委員会が日視連センター2階研修室で開催され出席しました。
全国委員会では、
1.令和7年千葉県での全国福祉大会に提出する議題を協議しました。 2.令和7年新潟県での全国視覚障害女性研修大会のレポートテーマを決めました。 3.第71回全国視覚障害女性研修大会新潟県大会の要項と申し込みについて、新潟県の水野常任委員より説明がありました。 4.日視連・竹下会長と各現状報告、日常生活での困りごとや意見などを話し合いました。
全国代表者会議では、
1.令和6年度行事中間報告と収支決算中間報告は承認されました。 2.令和7年度運動方針(案)と事業計画(案)の審議がされ、令和7年度収支予算(概算案)が承認されました。 3.第78回全国福祉大会千葉県大会への提出議題と第71回全国視覚障害女性研修大会新潟県大会でのレポートテーマが決まりました。 4.「あかね」について話し合いました。
5.令和7年新役員選挙が行われました。 阿部会長、原田副会長、渡邊副会長、水野副会長が継続して就任されました。
6.新役員から「2年間よろしくお願いします」と挨拶されました。
1.令和6年度第2回理事会
12月12日(木)14時よりライトセンター研修室において、理事10名・監事1名の出席により開催されました。
ここでは第1号議案・令和6年度事業報告について、会長から6月から12月までの間に開催された協会行事について概略が説明されました。
その後、各担当の業務執行理事の方からより具体的な行事報告がなされて、第1号議案が承認されこの日の理事会を終了。
2.令和6年度第3回理事会
令和7年3月27日(木)14時よりライトセンター研修室において、理事11名・監事1名の出席で開かれました。
第1号議案・令和7年度事業計画(案)について審議、続いて第2号議案・令和7年度予算(案)について審議。
最後に一括して質問を受けた後、第1号・第2号議案とそれぞれ分けて理事全員の承認をいただきました。
第3号議案・令和6年度事業報告について。
ここでは、令和6年12月から7年3月にかけての行事について、各業務執行理事の方から報告がなされ理事全員の承認をいただいてこの日の理事会を終了しました。
3.合同会議
3月30日(日)10時よりライトセンター研修室において開催されました。
この日取り上げられた議題としては、
(1)令和7年度事業計画案として、基本方針・事業の概要・センター事業・事業内容について事務局から報告がなされ、後に会長から具体的な説明。その中で、各支部長さん方には、県の協会行事と地元支部の行事が重ならないようお願いがなされました。
(2)令和7年度予算について事務局から説明がありました。
会長からは、大幅な赤字予算となっているので少しでも無駄を無くしていきながら進めてゆきたいとの方針が示されました。
(3)要望事項について。
ここでは令和7年始めに取りまとめる県への要望について出席者から意見を募ったところ、特に、読書バリアフリー法(障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法)の富山県における進展状況について質問が寄せられましたが、会長の方から数年前より県への要望としてお願いしているところですが、目立った進展はなく未だに解答が届かない状況である事が話されました。
終わりに会長から出席者の皆さんに向けて、昨年1月の能登半島地震の後、安否確認として自宅への固定電話へ連絡を取ろうと試みたところ、家屋の倒壊・ライフラインの切断などにより連絡が取れない状況が続いた事から、今後本協会では、緊急時の連絡先として、個人の携帯電話の番号をセンターに登録してほしいという要請がされました。
令和6年度最終の行事で、寒の戻り・冷たい雨の降る中、協会評議員・支部長・青年部・女性部・スポーツ各代表・相談役の皆様にお集まりいただき声を聞かせていただくことができ、有意義な一時となりました。
令和7年度も、本協会行事に一人でも多くの参加協力をお願いしたいところであります。
◎第32回 Uni-Voice(ユニボイス) (2025年3月26日)
今回は「ユニボイス」アプリ(視覚障害者のための情報アクセシビリティ向上ツール)についてです。
1.はじめに
視覚障害者にとって、日常生活の中で情報を得ることは大きな課題となります。特に、紙の印刷物に記載された情報を正確に読み取ることは困難であり、点字や音声案内のない資料では内容を把握することができません。こうした問題を解決するために開発されたのが「ユニボイス」アプリです。視覚障害者向けにユニボイスの仕組みや利用方法、メリットについて詳しく解説します。
2.ユニボイスとは
ユニボイスは、印刷物に埋め込まれた二次元コード(ユニボイスコード)をスマートフォンアプリで読み取ることで、テキスト情報を音声で読み上げたり、拡大表示したりすることができる技術です。
ユニバーサルデザインの理念に基づき、視覚障害者だけでなく、高齢者や外国人など、多様な人々が情報にアクセスしやすくなるよう設計されています。
3.ユニボイスコードの仕組み
ユニボイスコードは、QRコードに似た二次元コードであり、以下のような特徴を持っています。
・高い情報量:一般的なQRコードよりも多くの文字情報を格納可能。
・見やすいデザイン:印刷物に馴染むよう設計され、他の情報と併記しやすい。
・専用アプリでの読み取り:無料の「ユニボイス」アプリを使用して、スマートフォンで簡単に読み取れる。
ユニボイスコードを読み取ると、アプリが自動的に内容を解析し、音声で読み上げたり、画面に拡大表示したりします。
4.利用方法
視覚障害者が「ユニボイス」アプリを利用する際の基本的な手順は以下の通りです。
(1)アプリのインストール
・スマートフォンのアプリストア(App Store または Google Play)で「ユニボイス」アプリをダウンロードし、インストールします。
(2)ユニボイスコードをスキャン
・アプリを起動し、カメラを使用して印刷物に記載されたユニボイスコードを読み取ります。
(3)音声読み上げ機能の利用
・読み取った内容が音声で再生されるため、画面を見なくても情報を得ることができます。
・読み上げ速度の調整や、一時停止・再開が可能です。
(4)拡大・ハイコントラスト表示(弱視者向け)
・読み取った文字を拡大表示したり、背景と文字の色を変更したりすることで、視認性を向上させます。
5.利用シーンと導入事例
「ユニボイス」アプリは、さまざまな場面で活用されています。
(1)公共施設での利用
・市役所や区役所の窓口案内、パンフレット、公共交通機関の時刻表などに導入され、視覚障害者が情報を得やすくなっています。特に「耳で聞くハザードマップ」は災害時の安全確保の面で重要です。自治体からの緊急情報をスマートフォンの音声や見やすいフォント・コントラストで知ることができます。
(2)医療機関での活用
・病院の診察券やお薬の説明書にユニボイスコードを導入することで、患者が薬の服用方法を音声で確認できるようになっています。
(3)商業施設・観光案内
・レストランのメニューや観光パンフレットにユニボイスコードを印刷し、視覚障害者が自分で内容を確認できる環境を整えています。
(4)書籍・教育分野での活用
・点字が読めない視覚障害者でも、教科書や参考書にユニボイスコードを活用することで、内容を音声で理解できるようになります。
6.「ユニボイス」アプリのメリット
「ユニボイス」アプリの導入によって、視覚障害者の情報取得環境が大きく改善されます。
(1)情報アクセスの向上
・文字が読めない人でも、音声で情報を取得できるため、視覚障害者にとって非常に便利です。
(2)操作が簡単
・スマートフォンをかざすだけで簡単に情報が得られるため、特別なスキルがなくても利用できます。
(3)多様な人々に対応
・視覚障害者だけでなく、高齢者や識字困難者、外国人にも有用な技術です。
7.まとめ
「ユニボイス」アプリは、視覚障害者がより多くの情報にアクセスできるようにするための画期的なツールです。公共機関や医療機関、商業施設など、さまざまな場面で活用されており、今後さらに普及が期待されます。この技術が広まることで、視覚障害者の生活の質が向上し、よりインクルーシブな社会の実現につながるでしょう。
さて、大変すばらしいものだとして長々と説明してきましたが、難点もあります。最大の難点は「すべてを音声では操作できない」という点です。スマートフォンに「助けて」とか「困ってるの」とか話しかけても「ユニボイス」アプリは何もしてくれません。当たり前です。自分自身がスマートフォンを操作して必要な情報を引出し、次の行動を頭で考える経験を積まなければ便利なアプリも何の役にも立ちません。
結論、みんなで練習しましょう。
◎第33回 チャットGPT (2025年3月26日)
今回は今話題のAIが視覚障害者を助けてくれるのか、「チャットGPT」についてです。
チャットGPTは、テキストを用いた対話型のAIで、質問に答えたり、文章を作成したりすることができる便利なツールです。音声入力やスクリーンリーダーと組み合わせることで、視覚障害のある方も快適に利用できます。
1.チャットGPTとは?
チャットGPTは、人工知能(AI)を活用した会話型システムです。テキストを入力すると、それに応じた回答を返してくれるため、調べ物や文章作成、学習の補助、日常の疑問解決などに役立ちます。
例えば、以下のようなことが可能です。
✅ 知りたいことを質問:「〇〇について詳しく教えて」
✅ 文章の作成・添削:「メールの文章を考えて」「この文章を修正して」
✅ 読書や学習の補助:「歴史について簡単に説明して」
✅ 生活のアドバイス:「料理のレシピを教えて」「旅行の計画を手伝って」
✅ プログラミングのサポート:「Pythonのコードを書いて」
2.視覚障害者がチャットGPTを使う方法
① スマートフォンで使う
スマートフォンの音声入力機能やスクリーンリーダー(ボイスオーバーやトークバック)と組み合わせることで、チャットGPTを音声で操作できます。
○iPhoneでの利用方法
・「チャットGPT」アプリ(OpenAI公式)をアップルストアからダウンロード
・音声入力:キーボードのマイクボタンを押して話すと、テキストが入力される
・ボイスオーバー対応:読み上げ機能でチャットGPTの回答を音声で確認可能
○Androidでの利用方法
・グーグルプレイストアから「チャットGPT」アプリをダウンロード
・音声入力:グーグルの音声入力機能を使って質問
・トークバック対応:読み上げ機能で応答を確認
② パソコンで使う
パソコンでは、スクリーンリーダー(NVDA、JAWS、VoiceOverなど)と組み合わせて利用できます。
○ウェブ版の利用方法
(1)チャットGPT公式サイトにアクセス
(2)画面のテキスト入力欄に質問を入力(音声入力も可能)
(3)AIの回答をスクリーンリーダーで読み上げ
○Windowsの活用方法
・NVDAやJAWSを使って、チャットGPTのテキストを読み上げる
・Windowsの音声入力機能で、キーボードを使わずに質問を入力
○Macの活用方法
・Siriの音声入力を使ってチャットGPTに質問
・ボイスオーバー(macOS標準のスクリーンリーダー)を有効にする
③ スマートスピーカーで使う(将来の可能性)
現在、チャットGPTはグーグルホームやアマゾンエコー(アレクサ)には正式対応していませんが、将来的に音声アシスタントとして統合される可能性があります。
3.チャットGPTを活用するメリット(視覚障害者向け)
① 文章の作成や修正が簡単にできる
✅ メールや文章を作るのが難しいとき、文章の提案や修正をしてもらえる
✅ 敬語やビジネスメールのチェックも可能
② 情報検索がスムーズ
✅ インターネットで検索しにくい場合でも、チャットGPTに直接質問すれば回答を得られる
✅ 読み上げ機能と組み合わせると、音声で情報を聞ける
③ 学習や趣味にも役立つ
✅ 読書の要約や学習のサポート:「〇〇の内容を簡単に教えて」
✅ プログラミングの練習:「Pythonで〇〇を作るコードを教えて」
✅ 音楽・映画のおすすめ:「おすすめのクラシック音楽を教えて」
④ 日常の便利ツールとして使える
✅ スケジュール管理:「効率的なスケジュールを考えて」
✅ 買い物リスト作成:「買い物リストを作って」
✅ 料理のレシピ:「簡単に作れるレシピを教えて」
✅ 画像の説明:画像をチャットGPTと共有することで内容を文章で説明
4.チャットGPTを使うときの注意点
① 正確性に注意
・チャットGPTの回答は、必ずしも100%正確ではないため、特に医療・法律・金融などの重要な情報は専門家に確認が必要。
② 最新の情報には対応していないことがある
・一部のバージョンでは、最新のニュースや情報を取得できない場合がある。
・必要に応じて、ウェブ検索機能を活用すると良い。
③ プライバシーに配慮する
・チャットGPTは入力された内容を記憶しないが、個人情報や機密情報は入力しない方が安全。
5.チャットGPTのバージョンと利用プラン
① 無料版(GPT-3.5)
・基本的な質問や文章作成に利用可能
・一部の高度な質問には対応が難しい場合あり
② 有料版(GPT-4 Turbo)
・より高精度な回答が得られる
・文章の品質向上や長い会話が可能
・月額料金がかかる(チャットGPTプラス: 約20ドル)
無料版でも十分に活用できますが、より高精度な回答を求める場合は有料版の利用も検討できます。
まとめ
✅ チャットGPTは、視覚障害者の方にも便利な対話型AIツール
✅ 音声入力やスクリーンリーダーと組み合わせて利用可能
✅ 情報検索、文章作成、学習、日常のサポートなど幅広く活用できる
✅ 無料版と有料版があり、用途に応じて選択可能
チャットGPTを活用することで、日常生活のさまざまな場面で便利に情報を得たり、文章作成を効率化したりできます。興味があれば、ぜひ試してみてください。
さて、今回も長々と説明してきましたが、私はチャットGPTを様々な用途で実際に使っています。まずは調べもので、ウェブ検索してたくさんのページを読み、内容を統合するよりも圧倒的に早い。さらに文書作成では、圧倒的な情報量の「AI様」がちゃんとした日本語で書いてくれます。実は前回の「利便性委員会のお知らせ」32回と今回33回のほとんどは「AI様」が書いています。
最後のちょっと面白い話、チャットGPTは共有した画像の説明も詳しくしてくれます。私は弱視で写真に写っている人の表情や景色の詳細はよくわかりません。そこでチャットGPTに教えてもらってるわけですが、表情や景色から受ける人の感情がわからないから「AI様」に教えてもらっていることに、かなり複雑な感情です。
10月13日のこの日は、3連休の中日で天気は快晴でした。午前10時から富山市磯部町の視覚障害者福祉センターにおいて第48回視覚障害者文化祭、及び福祉機器展が行われました。
今年も昨年に続き完全な形で行われ、会員、付添い者、ボランティアの方約120名が参加しました。
午前10時に会長挨拶に続き邦楽演奏会があり、箏・尺八のコラボ演奏で、だれもがわかるスタンダードの曲、童謡、「ふるさと」や「花は咲く」などの演奏をしていただきました。
演奏後は、箏や尺八を実際に触ったり演奏したりと、なかなかできない楽しい時間を過ごしました。
その後の昼食は、皆さん自由に好みのコーナー(お茶席、便利グッズ、施術体験、AIスピーカー、囲碁体験、バザー、コーヒー、飲食物、ビアガーデンなど)の見学や体験を楽しみました。
便利グッズコーナーでは、エクストラ社のセンスプレーヤー、アマゾンのAIスピーカー・Echo Showなどを説明を聞きながら体験できました。
とくにセンスプレーヤーは興味深く質問しながら触っている方がおられ、有意義な時間でした。
午後1時から生きがい教室発表が行われ、フラワーコーラス、民謡、エアロフォン演奏、カラオケなど、日頃の練習成果を存分に披露されました。
施術体験では、日ごろお世話になっているボランティアの皆さんに施術をしました。
今年は天気も良く、フル開催ということで、多くの方が参加され、盛況のうちに終了しました。
ご協力をいただいた多くのボランティアの皆様、センター職員の皆様、また助成いただいた富山県共同募金会様、本当に有難うございました。
◆「第24回富山県障害者スポーツ大会(卓球競技会)」参加報告
第24回富山県障害者スポーツ大会(卓球競技会)は、令和6年11月10日に富山市秋ケ島の「富山県総合体育センター」において120人余の選手とそれを支えるボランティアの皆様、試合の審判をしてくださる富山県卓球協会レディース部の皆様のご協力を得て盛大に開催されました。
最初に9時20分から開会式が始まり、主催者代表の県生活環境文化部・スポーツ振興課の課長の開会のご挨拶、来賓としてお越しいただきました我らが富山県視障協会長塘添誠次氏からの激励のお言葉をいただいた後、9時50分から私たちのSTT競技は中アリーナで、その他の一般卓球は大アリーナのそれぞれのコートで試合が開始されました。
一般卓球に比べて、STT競技の方は、男女合わせても9人の出場しかなく、数年前のにぎやかさはなく先細りの感じがして寂しく感じられました。
富山県内にはまだまだ多くのSTT愛好者がいらっしゃると聞いています。ぜひともご参加いただきSTT競技を盛り立てていただきたいと願っています。県のクラブも選手の高齢化と新人選手の発掘ができずクラブ員数がだんだん減っています。ぜひともSTT愛好者は県視障協STTクラブにご入会いただき「みんなで盛り上げていただければ」と願っております。
それでも試合になると打球音がアリーナ内に響き熱戦が繰り広げられていました。この中アリーナの広さは想像している以上に広いらしく、3台設置してある卓球台の間隔はプレーに支障を与えることはありませんでした。
この大会は令和7年10月に滋賀県で開催される全国障害者スポーツ大会への予選会でもあり、1打1打に熱気がこもっていたように感じられました。
今年の佐賀大会に出場されました林大志選手は見事銅メダルを獲得されただけあって今日も打球音はさえわたっておりました。
大会終了後帰宅すべくセンターのバス停でバスを待っていると、ガイドヘルパーから「立山がきれいに見えますよ」と聞かされ改めて初冬の澄み切った空模様が感じられました。と、頭上高くで「ピー、ヒョロロー」とトビのなく声が響き、さわやかな気候にトビののどかな鳴き声で久しぶりにのんびりとした時間を過ごせた気がしました。
成績は次の通りです。
STT-A女子の部
優勝 徳市(とくいち)和美(かずみ) 2位 本江(ほんごう)とみ子(とみこ) 3位 森田(もりた)恵美子(えみこ)
STT-A男子の部
優勝 中西(なかにし)美雄(よしお) 2位 林(はやし)大志(ひろし) 3位 川口(かわぐち)勇人(はやと)
私がiPhoneに機種変したきっかけは、2018年の11月のある日のことです。いつものようにガラケーをズボンのポケットに入れてトイレに行きました。
その時、音がしたので慌ててズボンを触ったら、なんとなんと、ガラケーがありません!
まさかと思い、便器の中を触ったらやはり落ちていました。まだトイレをする前だったので良かったのですが、トイレをした後だったら大変でした。
バッテリーを外してドライヤーで乾かして、とりあえず電源を入れ直しました。防水が効いていたので何とか復活しましたが、いずれ使えなくなると困るしと思い、休みの日にiPhoneに詳しいサポーターの方と一緒にショップに行きました。
何度かiPhoneには触っていましたが、やっぱりこんなもの使えるだろうかと頭をよぎっていました。
でも、いずれガラケーはなくなる、早く少しでも触り慣れないと、と言う気持ちが勝っていましたので、その日にiPhoneに機種変更しました。
その日にVoiceOverの設定もしてもらい、とりあえず最低限度の電話の取り方切り方を聞いて後はSiriで何とか使えるように設定してもらいました。
一応VoiceOverのジェスチャーなどは調べていたのですが、なかなかうまくできないのは事実でした。トラブルもたくさん経験しました。
パスコードロックがかかって電話をかけることや取ることもできない状態になりました。
月日が経ち、1年ぐらい経った時からショッピングアプリなども入れました。ずっと楽しみにしていたネットショッピングの再会です。楽しくお買い物ができるようになってうれしかったです。
ガラケーの時よりも使い勝手は良いような悪いような?でしたが、使い慣れていくうちに、どんどん、どんどん楽しくなってきました。
そうなると欲が深くなっていろんなアプリを入れたくなり、インストールしています。今ではiPhoneと共に起きてiPhoneと共に日々を送っています。
朝、電気がついたかを確認するアプリから開始し、ニュース、天気予報、LINE、メール、銀行や郵便局の入出金等、クレジットカードの利用状況、そしてショッピングカードの利用状況、ポイントなどを確認しています。
今まではできなかったことが、このiPhone1つでできるようになり本当に私の生活は変わりました。
災害になった時は白杖、障害者手帳等が入ったカバン、iPhone関連一式、そして薬等を持ち出せるようにしておきます。
やはり私の1番大事なものは命、そしてiPhoneかな。何よりも私をiPhone生活にしてくれた人たち、そして何よりも心遣い良いサポーターの方々、そしてアドバイスをくれる仲間の存在が大切です。
いろいろなカテゴリーのアプリがある中、何よりも見えなかった文章を読んで聞いて確認できる。これはとっても画期的なことでした。
更に、今まで日常生活用具でもらっていた物がアプリ1つでできたりする物もあります。
私にとって1番大切なアプリは「Be My Eyes」(私の目になって)です。その名の通りのアプリです。
スマホのカメラで私たちが見たい物を写し、それをボランティアさんが見て教えてくれると言うアプリです。横にいて「ねぇねぇちょっと見て欲しいんだけどお願いします」って感じで、気軽にアプリを立ち上げてサポートボタンを押します。そうすると、登録しているボランティアさんに一斉送信され、日本を問わず世界各国のボランティアさんがそれに気づいた人が私の目の代わりになって教えてくれます。
今まで何十回、何百回使ってきて、助けていただきました。
私は本当に不器用で機械音痴だけど、ドラえもんの「どこでもドア」ではなく、私の「ポケット秘密兵器」なのです。
自分の生活を支えるためにもとっても大切なものなのです。やっぱり最初は抵抗がありますが、触って触って触り倒す。そうしないと自分の物にならないのです。
困った時は助けてくれる仲間、そしてiPhoneを使い慣れているユーザーさんのサポートを仰ぎながら日々奮闘している毎日です。
今、「この世からなくなって困る物は?」と聞かれたら、やっぱりiPhoneですね。
本当、トラブルは誰よりもたくさん起こしたし、普通の人が起こさないことを私は先駆けてやってしまっていて、「なんでそうなったのか?」説明はできませんが、でも誰かちゃんと助けてくれるんです。
もちろん、自分でもどうしてそうなったのか、不思議に思って調べることもありますけれど、やっぱりiPhoneを使っててよかったなぁって思うのはたくさんのユーザー仲間がいることです。
もしこの文章を読んでくださっている方で、まだ、らくらくスマホやガラケーユーザーで、iPhoneをためらっている方がいましたら、こんな私でも使えてるんだから大丈夫だよ、と言います。
そして、困った時は声を出してくれればきっと助けてくれる必ず助けてくれるそんな仲間はたくさんいるんだよ、と声を大きくして言います。
本当、自分の生活はiPhoneによって様変わりしました。できなかったことができるようになる秘密兵器なのです。皆さんも秘密兵器を持ちましょう。
富山県知事表彰(ボランティア部門功労者表彰)
四宮(しのみや) 一子(かずこ)氏 R6.10.10
とやま県民スポーツ大賞 最優秀賞(ミドル・シニアアスリート部門)
中西(なかにし) 美雄(よしお)氏 R7.2.18
受賞おめでとうございます。
10月13日(日) 第48回視覚障害者文化祭・福祉機器展(センター)
アトラクション「邦楽演奏会」
生田流筝曲正弦社 直門大師範
正弦社かたかご会代表 水谷 佳代氏
都山流尺八 竹琳軒大師範
邦楽ネットワーク富山主宰 東海 煌山氏
会員51名 ボランティア39名
10月19日(土)・20日(日) 第33回北信越サウンドテーブルテニス大会(石川県) 6名
10月26日(土)~ 28日(月) 第23回全国障害者スポーツ大会(佐賀県)
11月10日(日) 三療研修会(センター) 18名
11月30日(土)・12月1日(日) 第10回日本視覚障害者団体連合北信越ブロック大会(新潟県) 16名
12月3日(火)~ 9日(月) 障害者週間
12月8日(日) 更生相談会・結婚相談室・意見交換会(センター) 33名
12月12日(木) 理事会
12月末 会報『ゆきしろ』第90号発刊
― 令和7年 ―
3月27日(木) 理事会
3月30日(日) 合同会議
4月20日(日) (第25回富山県障害者スポーツ大会~水泳競技)(高岡総合プール)
5月22日(木) 理事会①(センター)
5月25日(日) (第25回富山県障害者スポーツ大会~陸上競技)(県総合運動公園)
5月25日(日)・26日(月) 第78回全国視覚障害者福祉大会(千葉県)
6月8日(日) 第52回北信越グランドソフトボール大会(石川県)
6月15日(日) 定時評議員会(センター)
6月15日(日) 理事会②(センター)
6月15日(日) 定期会員総会(センター)
6月末 会報「ゆきしろ」第91号発刊
7月6日(日) ボランティアと利用者交流会(センター他)
7月27日(日) センタークリーン作戦(センター)
8月21日(木)・22日(金) 北信越会長会議(福井県)
8月24日(日) 第74回点字競技会・第26回パソコン競技会(センター)
8月30日(土)・31日(日) 宿泊研修(歩行訓練・研修会)(魚津市)
9月3日(水)・4(木) 第71回全国視覚障害女性研修大会(新潟県)
9月14日(日)・15日(月) 第71回全国視覚障害青年研修大会(愛知県)
9月21日(日) (第25回富山県障害者スポーツ大会~フライングディスク競技)(県総合運動公園)
9月28日(日) 第51回球技大会(グランドソフトボール・サウンドテーブルテニス)(センター他)
10月12日(日) 第49回視覚障害者文化祭・福祉機器展(センター)
10月18日(土)・19日(日) 第34回北信越サウンドテーブルテニス大会(富山県)
10月25日(土)~27日(月) (第24回全国障害者スポーツ大会)(滋賀県)
11月9日(日) (第25回富山県障害者スポーツ大会~卓球競技)(県総合体育センター)
11月9日(日) 三療研修会(センター)
11月29日(土)・30日(日) 第11回北信越ブロック大会(長野県)
12月3日(水)~9日(火) 障害者週間
12月7日(日) 更生相談会・結婚相談室(センター)
12月7日(日) 意見交換会(センター)
12月11日(木) 理事会③(センター)
12月末 会報「ゆきしろ」第92号発刊
-令和8年-
3月26日(木) 理事会④(センター)
3月29日(日) 合同会議(センター)
通年
・点訳、朗読奉仕員養成・研修事業 ・外出介護サービス指定事業者情報提供事業 ・生活訓練事業 ・盲導犬育成事業 ・結婚相談事業 ・福祉機器相談事業 ・三療研修会 ・IT推進員派遣事業
今年は雪が多く、盲導犬歩行でウォーキングを楽しみとしている私には厳しい冬でした。また、日々の気温差の激しさにも悩まされました。
そんな中でも、視覚障害者協会は着実な活動を続けています。その記録がこの『ゆきしろ』です。世の中の人に視覚障害者を理解していただく参考になれば幸いです。
また、会員の皆さんは、多様化が進む現在、いろんなことにチャレンジしてほしいと思います。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆